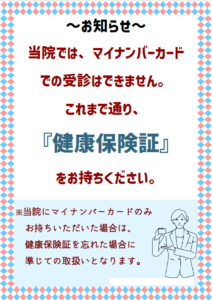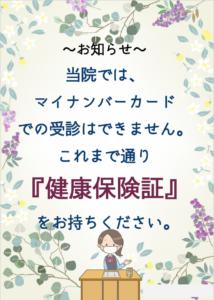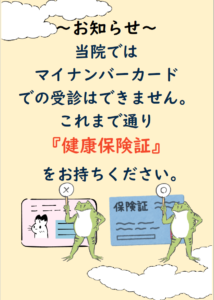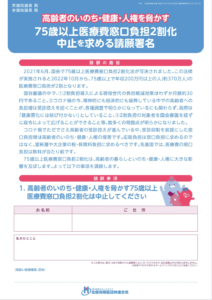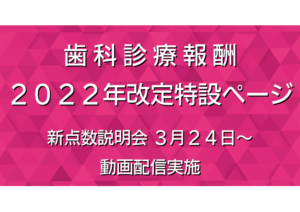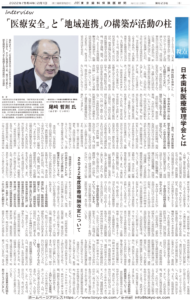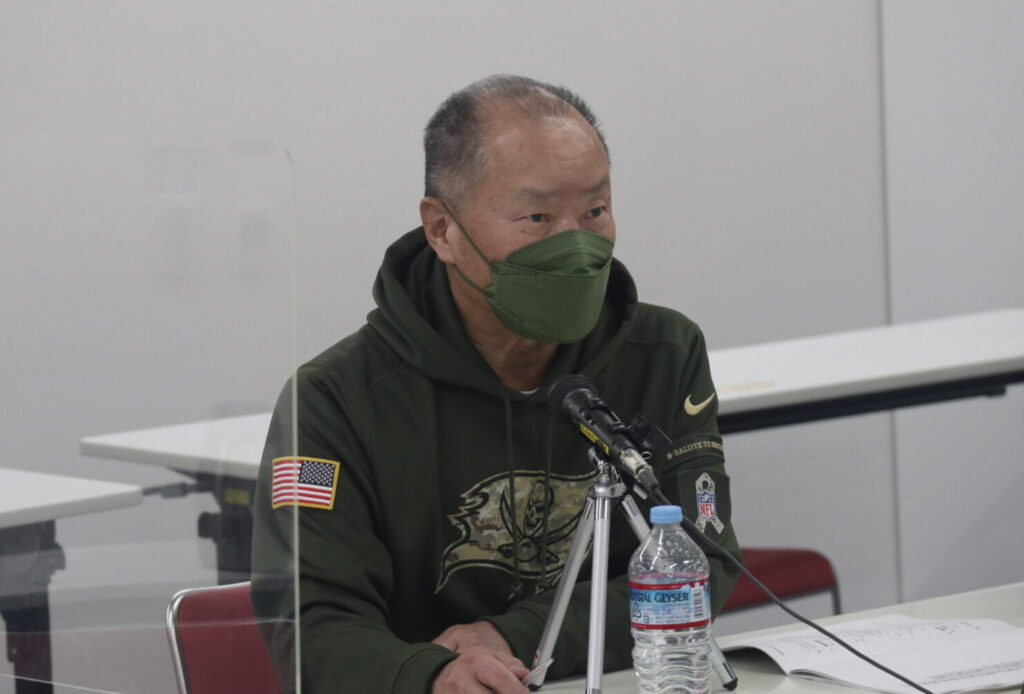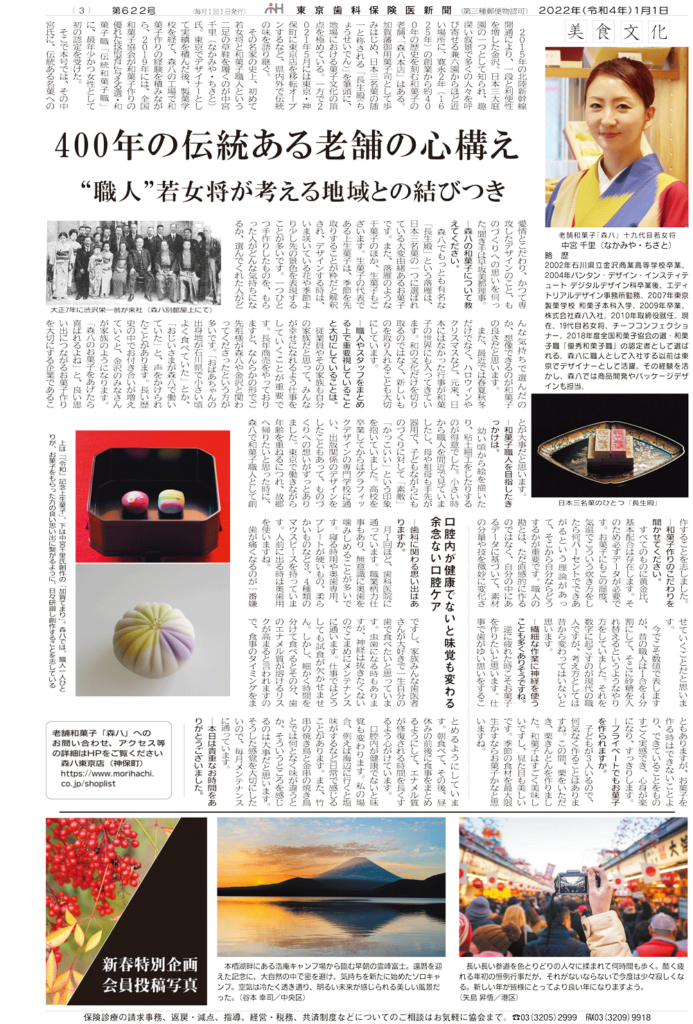過去に類なき異例事態が医療界で勃発/次期2024年度診療報酬改定も新事態に備えを
◆界初認知症薬が大混迷米国でも保険適用がピンチに
最近、気になるニュースが2つある。一つは、アルツハイマー病(AD)治療薬「アデュヘルム」を巡る動きだ。ADの根本原因に働きかけ、症状の進行を遅らせると謳う薬剤としては、米国食品医薬品局(Food and Drug Administration/略称「FDA」)から世界初の承認をもらった。昨年6月のことだ。
アデュヘルムは、「ブロックバスター(大型薬)間違いなし」との華々しい船出であったが、その後の混迷ぶりがすさまじい。
まず、欧州や日本では承認が否決、保留された。さらに米国でも、AD患者の大半を占める高齢者向け連邦政府保険の当局が、今年1月に保険適用に厳しい条件を付ける案を出した。臨床試験(治験)参加の患者に限るというものだ。
4月に予定される最終決定もこの通りになれば、年間320万円の高額薬(これでも当価格から異例の半額値下げの結果だが)のため、まず売れないことになる。「事実上、この薬は死んだ」という声さえ市場では出ている。
米国の連邦政府内で、薬の承認当局と保険償還を決める役所で判断が真逆の方向になる異例の事態が生じているわけだ。
この混乱の原因は、承認申請に使ったこの薬の臨床試験(治験)での有効性データが不確かだったことにあるのだが、その背後には、①膨大な患者とその家族の窮状を救うこと、②薬事承認・保険償還での科学的エビデンスの確保、③保険財政への巨大インパクトとの折り合いをどうするのか―など、極めて現代的かつ社会的課題が存在している。
◆保険適用除外も検討課題?製薬団体トップが異例の発言
「おやっ」と思ったのはもう一つ。今年1月の日本製薬工業協会(製薬協)の岡田安史会長の「公的保険給付範囲の見直しに関する国民的議論が必要」との発言だ。医薬品の保険償還対象を狭めることも検討に値する、というものだ。
1個社ではなく、製薬団体のトップが、自らの権益縮小につながりかねないことに踏み込むのは、これまでは一種の〝タブー〟だった。超異例発言である。
その背後には、少子高齢化が山場を迎え、構造的に膨らむ日本の医療保険財政問題がある。診療報酬改定で、医科・歯科・薬局に比べさらにきつい寒風にさらされるのが製薬業界の定位置だ。すでに、薬価改定の毎年実施も始まっており、最近は、後発薬や特許切れ先発薬(長期収載品)の引き下げはある程度甘受しても、利益柱の特許新薬の薬価だけは死守しようという姿勢が製薬業界トップには見え隠れしていた。
しかし、ここからさらに踏み込んで来たため、追い込まれている業界事情をさらに強く感じさせる出来事となった形だ。
中医協の2022年度診療報酬改定の答申の付帯意見にも「保険給付範囲の在り方等への議論」の検討が盛り込まれた。製薬団体のトップの発言も背景にして、次回の2024年度改定に向け本格論議に発展するとの声も出始めている。
◆財務省が垣間見せる診療報酬改定の基礎資料変更
この2つの例を持ち出したのはほかでもない、医療界、それも先進国に共通して現在進行している事情、すなわち、高齢化に伴う公的医療財政の膨張という難題を背景に、過去の延長戦にとどまらない事態が生じている、ということを知ってほしかったからだ。これは歯科医療界においても(医科も薬局もだが)他人事でない。
2022年度診療報酬(本体)は昨年末に決着した。その結果も厳しかったが、その結果以上に、さらに将来の厳しさを感じさせたのが、決定に至るまでの過程だ。
公的医療財政膨張阻止に向け、財務省は「本体報酬のマイナス改定」に猛攻勢をかけて来た。
個人的に気になったのは、「医療経済実態調査」(以下、「実調」)に財務省が矛先を向けて来たことだ。実調は2年に1回、厚生労働省がこの診療報酬改定に合わせて全国の病院と一般診療所、歯科診療所、保険調剤を行っている保険薬局についてサンプル調査を実施。その集計結果に基づいてまとめるもので、現時点では医療機関の経営状況を示す唯一の総合的なデータだ。
厚生労働省や医療機関は、診療報酬本体の引き上げ要求にあたり、この実調データを使っている。
今回、この実調について財務省は、①サンプル調査数の乏しさ、②サンプル先が入れ替わることによる経年的把握の困難さ、③サンプルのバイアス・統計的な有意性―など、様々な問題点を指摘し、診療報酬改定に向けた基礎資料としての適格性に疑問を提起している。データとして痛いところを突いているとともに、過去に類のない異例の事態だ。
財務省資料が挙げる一例では、実調の診療所のサンプル数は診療所全体の20分の1、有効回答率56.2%を掛け合わせると診療所全体の2.8%のデータしか捕捉していない。歯科診療所も同様に全数の1.1%の捕捉率だ(ともに平成29年調査)。医療機関全体の状況を正確に示しているとはいえず、実態と乖離がある、というのが財務省の主張だ。
代わりに財務省が推すのが「医療法人事業報告書等」というデータだ。医療法人全数を対象に、毎年届け出義務のあるデータを基にまとめた資料だ。これなら確かにサンプルバイアスはなし、経年比較もでき、診療報酬改定などの病院等経営への影響も、より正確に捕捉しうる。厚労省はこのデータの届け出や公開(閲覧)でのデジタル化を進めている。財務省はこのデジタル化を間に合わせた上で、医療法人事業報告書等を次期2024年度診療報酬改定の基礎資料にしようという狙いを垣間見せている。
歯科医療界はこれにどう対処するのか。どう診療報酬改定にこれが影響するかの見通しを持っているのか。今から考えておく必要があるのではないだろうか。
東洋経済新報社編集局報道部記者 大西富士男
「東京歯科保険医新聞」2022年3月1日号10面掲載