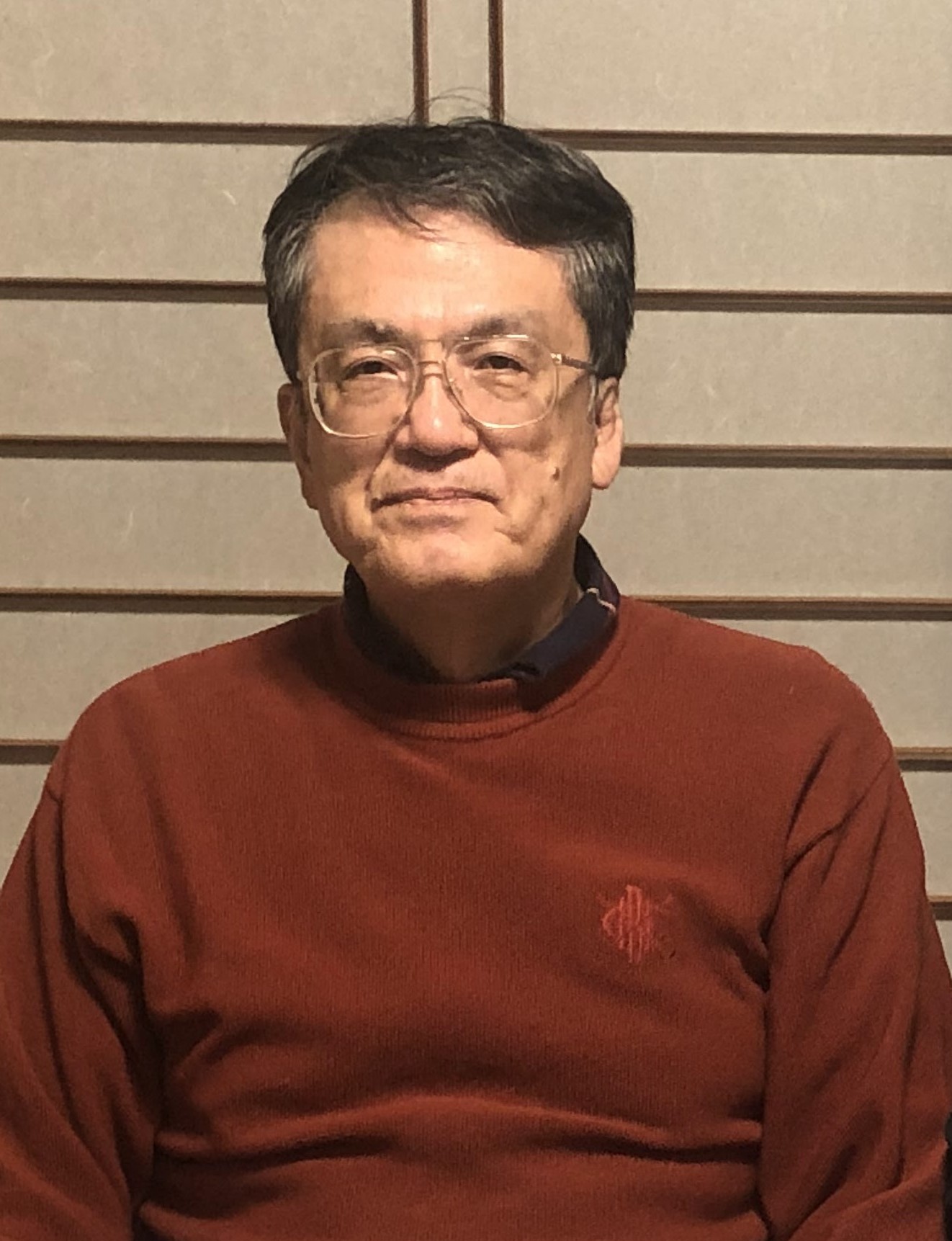「能登・被災診療所のいま(後編)/ 被災1年―懸念は高齢避難者の口腔機能低下」
石川県保険医協会副会長 平田 米里/平田歯科医院
3月11日、東北地方を中心に甚大な被害をもたらした東日本大震災から14年が経過した。2024年は元旦に能登半島地震が発生し、石川県保険医協会会員の歯科診療所が被災した。地域医療の一端を支える各地の歯科保険医は、こうした災害とどのように向き合ってきたのか。宮城県保険医協会・井上博之理事長、石川県保険医協会・平田米里副会長に綴ってもらい、今回は平田氏の後編を掲載する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆地道な活動で被災会員の傷を
この1年、石川県保険医協会はどのような活動をしてきたのでしょうか?義援金を届けるばかりではなく、政府広報資料の迅速かつ正確な情報提供に努めてきました。それも大事ですが、今、私が思うに、協会事務局による会員の安否確認に始まり、被害状況の聞き取り、その後の状況把握など、何度も現地に足を運び、被災した会員と直接言葉を交わしながら、強い関係性を構築してきたことが最も大切な活動であったのではないでしょうか。こうした地道な活動によって被災した会員の心の傷を少しは癒すことができたのではないかと思っています。
後に、能登総合病院の口腔外科医の危惧を紹介します。彼は言います。「確かに発災直後は歯科診療車に代表されるような緊急対応が必要だった。1年を経過した今、仮設暮らしの通院困難な高齢者の口腔機能低下が心配だ。その分野の歯科需要は、今後の課題として浮上してくる。対応を準備しなければならない」―と。
能登には仮設住宅で暮らす人のほかに、遠方に避難したまま、意に反して帰宅できないでいる人も多い(事実、避難所の多くは既に閉鎖され、現在は仮設住宅に移っている方がほとんど。石川県内では2024年12月末時点で少なくとも2万699人が仮住まいや避難を余儀なくされている)。石川県の創造的復興プランにみられるような抑制的予算に縛られることなく、今こそ、能登に住み続けたいと願う人に、国が本来の責務を果たすべきでしょう。(完)
「石川県創造復興プラン」提言の賛同へのお願い
「『石川県創造復興プラン』検討会議」は2024年7月31日、石川県が策定した「石川県創造的復興プラン」に対して「提言」をまとめ、石川県に提出しました。
この提言には「住み続ける権利の保障」=「被災者・地域住民が、どこに、だれと住むか、どのように住むかを自己決定し、自分らしく生き、自己の願い・希望を実現することを人権として保障する」という視点から、県復興プランに対して9項目の提言を行っており、東京歯科保険医協会も団体として賛同しています。同検討会議では、広く賛同者を募集しています。ご賛同いただける方は、下記URLからお申し込みをお願いします。
<当協会・矢野理事より>
東日本大震災の時と違い、能登半島地震に対して具体的には何もすることができませんでした。1年以上経過しても復興への道は見えてきません。せめて被災地域への一助となればと思い私も復興プランの提言に賛同しました。ぜひ皆さまもご協力ください。